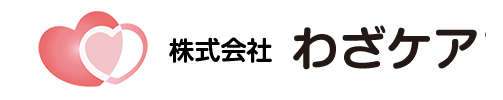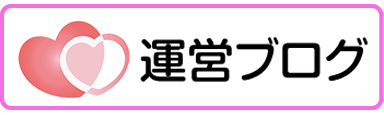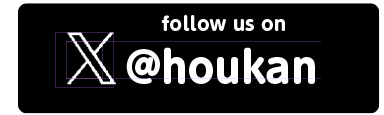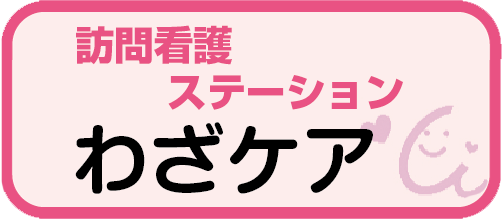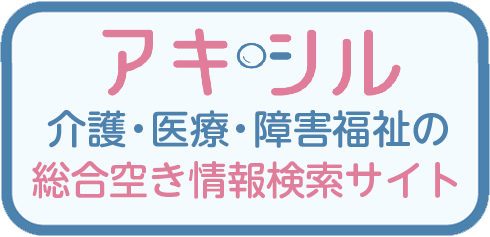代表挨拶
穏やかに自宅で過ごせるように
健やかに働き続けられるように
そしていつまでも賑やかな地域で
あり続けられるために私たちは支援します。
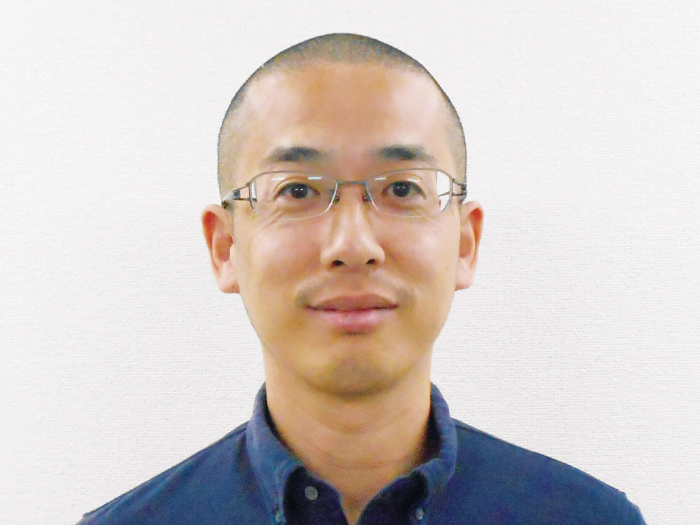
訪問看護ステーション
わざケア代表
渡部 達也
はじめに
就職氷河期世代の私は、手に職をつけたいという想いと祖父が脳卒中で身体が不自由だったとういうこともあり、自然とリハビリ専門職である作業療法士を目指していました。
作業療法士になってからは病院でリハビリ業務に携わりながら、職能団体の活動を通じて地域支援のお手伝いもさせて頂きました。
地域支援を行っていくうちに実生活の場でリハビリの支援をしたいという気持ちが次第に強くなり、2012年2月株式会社わざケアを設立、同年4月に訪問看護ステーションわざケアを開所し、実生活の場でリハビリ支援をするという夢を叶えることができました。(注 訪問看護ステーションには看護師だけでなく、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士も所属することでき、訪問看護ステーションから訪問リハビリを提供することができます)
開所当時、仙台市太白区内の訪問看護事業所の数は少なく、「訪問看護って何?」「リハビリが家でできるの?」とまだ十分認知されていないサービスでしたが、それから12年。地域包括ケアの考えが徐々に浸透していく中で訪問看護ステーションわざケアとしても大分地域に根ざすことができたと感じています。
今後も訪問看護・訪問リハビリは当社の地域支援サービスの核として充実させていきたいと思っておりますので、これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

介護ロボット開発・実証・普及事業から

介護人材不足の深刻化は、地域で生活し続けることを困難にしてしまう大きな原因になります。 持続可能な地域にするために私も地域支援している1人として介護人材不足を何とかしたいとの思いで、厚労省主管介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム構築事業として青葉山リビングラボの委員の1人としてお手伝いしています。 また、多くの介護事業所の介護生産性向上の一助になればと、『介護・医療・障害福祉の空き情報サイト アキシル』を開発し公開しています。 まだ使い勝手の部分など未熟な部分も多いのですが、ぜひお使い頂きまして多くの皆様のご意見頂ければと思っております。
職業病の解消から戦略的健康経営へ
将来必ず介護人材不足時代に陥りますので、現役世代は今から介護状態にならないように対策をしておく必要があります。 現役世代の対策として注目して頂きたいのが、仕事での「腰が痛い…」「膝が痛い…」いわゆる『職業病』です。 この『職業病』の放置は、従業員を将来介護状態にしてしまう要因になるだけではなく、企業に健康経営の考えが広まってく中で、企業に大きな損失を生んでいる可能性があることが分かってきました。 働き方改革が進み、企業は働きやすい職場づくりに取り組んでいますが、『職業病』 に関しては、「この職に就いている以上、仕方がない」 「みんなだって我慢している」と、企業も従業員も真正面から向き合うことは少なかったようです。 そこで、私たちは各企業に対し、『職業病』 の正体を突き止め、『職業病』 によって生じる損失を減らし、『職業病』を一緒に退治するお手伝いを開始しました。 短期間で成果が出てくる企業支援ではありませんが、長期的に 『健やかに働き続けることができる従業員を増やしていくこと』ができる支援となっています。 『元気で活き活きとした従業員』 は事業運営において最重要な経営資源であり、持続的に成長していくための大きな礎となります。従業員の将来に向けての介護予防にもつながります。『職業病』を一緒に退治しながら、健康経営を深化させて頂ければと思います。


代表経歴
昭和51年生まれ 辰年しし座B型 福島県生まれ
国立仙台病院附属リハビリテーション学院卒業
医療法人社団北斗病院、医療法人岩切病院、国立仙台病院、国立病院機構西多賀病院勤務後
平成24年2月 株式会社わざケア設立
平成24年4月 訪問看護ステーションわざケア開所
平成30年~介護ロボット事業
令和2年~東北大青葉山リビングラボ委員
令和4年12月 空き情報検索サイト アキシル開設 令和5年7月 健康経営しあえる開始
資格
作業療法士、居宅介護支援員、健康経営アドバイザー
趣味
読書 登山 ゲーム ドライブ バイク